現場に立たせてバトンを渡す。ゴールへ導いてもらえるように。
その後、京都大学大学院の博士課程を修了。28歳にして大学講師になった。竹中さんは今も、憧れだった太田先生のように話術で学生たちを引き込み、歴史の面白さを伝えている。ことあるごとに現地に赴き、そこかしこに残る先人たちの息づかいを感じさせながら。


「歴史学はな、過去を通して、現代の問題を解決するための手段。だから現場に立つことが大事。現地に行けば、求めているものの姿がおぼろげながら浮かび上がってくるのは、学問でも芸術でも、取材でも同じだろ?そして、歴史を学ぶうえでもう一つ大事なことは、今あるものを当たり前と思ってはいけないってことなんだ。例えば、ペンをこうやって持つ、書くときはまっすぐ背筋を伸ばして座る。それって当たり前だろ?でもそんなこと、いつ誰がなんのために決めたんだ?だって少し前まで畳に正座して筆で書いていたんだもの。時間だってそう。遅刻はダメとかすぐ言うけど、時計が普及するまで時間なんて誰も守れない。時間厳守のモラルって、たったこの100年足らずのことなんだよ?すべては歴史がつくってきたもの。歴史の中で、そうあるべきだと刷り込まれてきたもの。私たちは当たり前を当たり前と受け入れているけれど、それではいけない。今の常識が昔は非常識であったし、かつての常識が今では非常識だ。僕は歴史学を通じて、学生たちに常識を揺るがせることの大切さを伝えていきたい」

目に映るものひとつひとつ、そして感情や行動でさえも、歴史のなかでつくられてゆく。そしてそこにはいろいろな人の思惑や時代背景、政治的要素がはたらいている。それらを“知らない”ままで歴史の中に身を置いていることは、なんともったいないことだろうか。そうした、人間の“知りたい”という欲求と、知ってしまったからこそ何かを“変えたい”という欲求こそが、また歴史をつくり上げていくのだろう。「歴史はいつだって、常識に抗って立ち上がったマイノリティが作る。その声に耳を傾けるのがマジョリティだ」。竹中さんはそう付け加えて、真剣なまなざしを私に向けた。
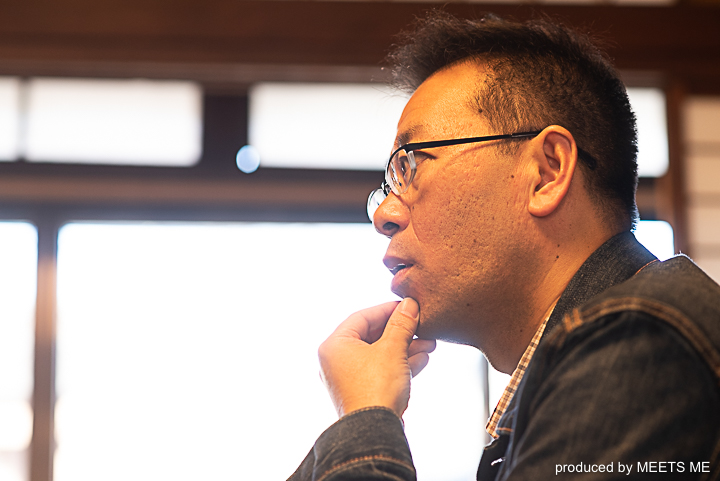
竹中さんはこれからも、こうしたスタイルの授業を貫いていくという。今後についての思いを尋ねた。
「地道に、目の前の50人、100人に向けて、歴史学の面白さを伝えていきたいかな。そうすると、学生たちが大人になったころ『そういえば先生、あのときあんなこと言ってたな』って思い出すかもしれないだろ?するとそこに現実に対する疑問が生まれる。それに共感した誰かがまた問題を提起して、社会に訴えて運動や革命になっていくかもしれない。そうして歴史はつくられ、続いていくんだ。奴隷制度廃止だって、民主主義だって、女性や子どもの人権だってそう。『常識』を覆してきたから実現したんだ。だから僕にできるのは、100年後の未来のための1歩を踏み出すこと。僕は第一走者としてバトンを渡すから、後世を生きていく人々がゴールに向かって走ってほしい。過去から渡されたバトンを強く信じた人が、歴史をつくっていくのだから」

自分の起こした行動がすぐにゴールに直結するのなら、それはそれでいいことだ。しかし今は評価されなくとも、強く信じて行動し続ければ、いつか誰かが自分の意思を引き継いでゴールに導いてくれる。今、ダメでも諦める必要なんてない。歴史という長い時の中で見れば、目の前の挫折なんて些細なこと。大切なのは、第一走者になることなのだ。何メートルの距離を走るかなんて、走ってみなくてはわからない。ゴールも見えないかもしれない。
けれど私たちの祖先は、ずっとそうして、時を紡いできたのだ。

やはり、竹中先生の講義は面白かった。大学のころとなにも変わっていない。この年齢になって改めて先生を訪ねて、また新しい学びがあったように思えた。
人は、いくつになっても学び続けていくのだ。
さて、私は、どんなバトンを誰に渡すのだろう?
そしてあなたは?
まだ見ぬゴールへと走り出す準備は、できているだろうか。
Text:光田さやか
Photo:荻野哲生

コメント